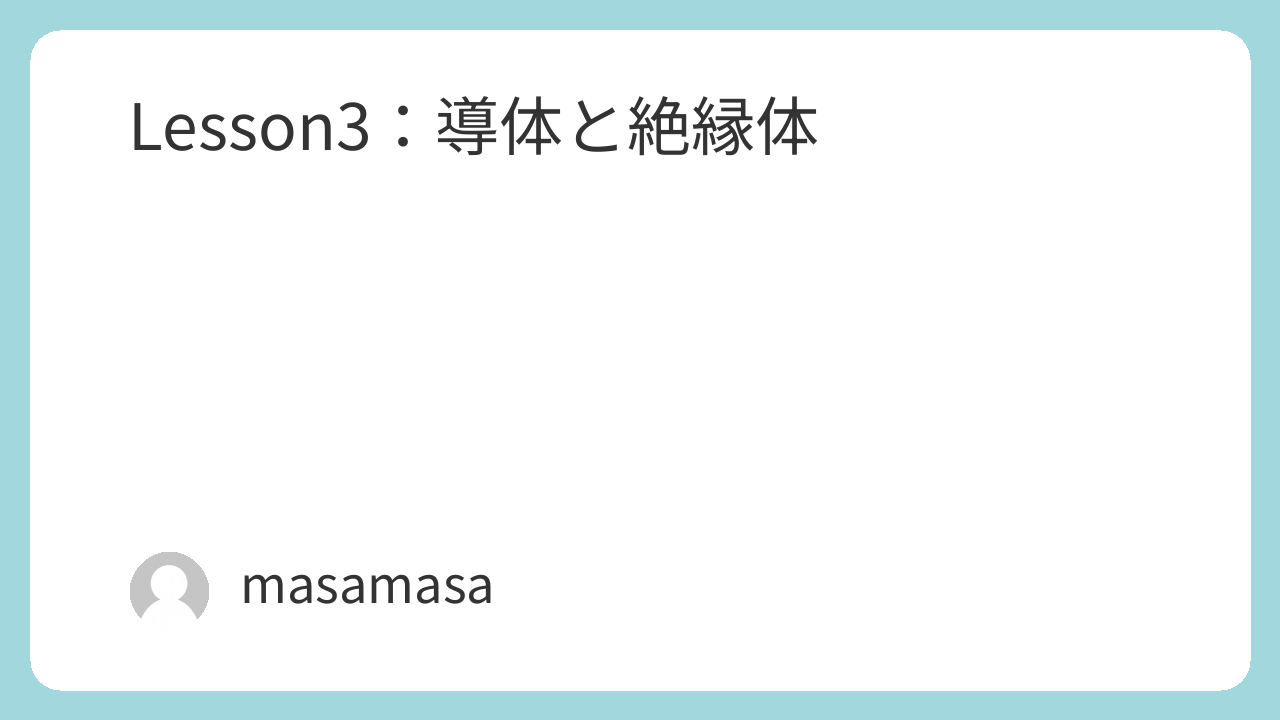電気って“流れるもの”っていうけど、どこでも流れるわけじゃないんだよね?





そうです。流れる道を作るのが『導体』、逆に止めるのが『絶縁体』です。





なるほど!でも、どうしてそういう違いがあるの?





今日はその仕組みを、電気工事士の教科書をもとに、やさしく整理していきましょう。
導体と絶縁体とは?
電気が流れる物質を「導体」、流れにくい物質を「絶縁体」といいます。
これは、物質の中にある電子の動きやすさによって決まります。
- 導体(どうたい):電子が自由に動ける。
→ 例:銅、アルミニウム、鉄などの金属。 - 絶縁体(ぜつえんたい):電子がほとんど動けない。
→ 例:ゴム、ガラス、プラスチック、木など。
💡 ポイント
電気は電子の移動によって流れます。
電子が動けるかどうかで、「流れる」「流れない」が決まるんですね。
導体にも“流れやすさ”の違いがある?
導体といっても、全て同じように電気が流れるわけではありません。
実は、材質によって電気の通りやすさ=抵抗(レジスタンス)が違うのです。
たとえば教科書には、以下のような比較が載っています👇
| 材質 | 抵抗率(Ω・mm²/m) | 特徴 |
|---|---|---|
| 銅 | 約0.017 | とても電気が流れやすい。電線に多く使われる。 |
| アルミニウム | 約0.028 | 銅よりやや劣るが軽くて安い。送電線に使われる。 |
| 鉄 | 約0.098 | 抵抗が大きい。発熱しやすい。 |
| ニクロム | 約1.10 | 抵抗が大きく、電熱線に利用される。 |
※抵抗率は温度によって変動します。





電気を通しすぎても困る場面もあるんだ。
例えば、ヒーターは“通りにくい金属”をわざと使っているんだよ。





なるほど、通りにくいから熱になるんだね!
抵抗の大きさは「長さ」と「太さ」でも変わる
電線の長さや太さも、電気の流れやすさに関係します。
- 長い導線ほど、電子の通る道が長くなって抵抗が大きくなる。
- 細い導線ほど、電子が通れる道が狭くなって抵抗が大きくなる。
この関係は次の式で表せます: R=ρ×l/S[Ω]「抵抗の法則」
ここで、
- R:抵抗(Ω)
- ρ:抵抗率(材質ごとの値)
- l:導線の長さ(m)
- S:断面積(mm²)
💬 覚え方:「細くて長い導線ほど電気が流れにくい!」
温度が上がると抵抗も上がる?
金属の導体では、温度が上がると電子の動きが乱れ、抵抗が大きくなります。
逆に、温度が下がると電子の流れがスムーズになり、抵抗が小さくなります。
| 状況 | 抵抗の変化 | 例 |
|---|---|---|
| 温度上昇 | ↑ 抵抗が増える | 夏場の電線、発熱体など |
| 温度低下 | ↓ 抵抗が減る | 寒冷地の電気配線など |





だから、冬と夏で電線の特性がちょっと変わることもあるんだよ。





これは工事士試験でも出そうなポイントだね!
🔢実際の測定と計算(例題)
教科書にある例題を簡単にまとめます。
例題
銅線の長さ20m、断面積2.0mm²のときの抵抗を求めなさい。
銅の抵抗率 ρ = 0.017(Ω・mm²/m)
\(R=ρ×\frac{I}{S}[Ω]\)「抵抗の法則」
R=0.017×20÷2.0=0.17Ω
R = 0.17Ω
- R:抵抗(Ω)
- ρ:抵抗率(Ω・mm²/m)
- l:導線の長さ(m)
- S:断面積(mm²)
答え:0.17Ω
💡 ポイント:導線が長くなると比例して抵抗も増える。
📌導体と絶縁体の学び直しポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 導体 | 電気を通す(金属など) |
| 絶縁体 | 電気を通さない(ゴム・プラなど) |
| 抵抗率 | 材質によって決まる「流れにくさ」 |
| 長さと太さ | 長い=抵抗大、太い=抵抗小 |
| 温度 | 上がると抵抗も増える(特に金属) |





電気の通りやすさって、材質・長さ・太さ・温度の4つで決まるんだね!





その通り!この基礎を押さえておくと、配線設計や工事士試験にも役立つよ。
📝まとめ
電気の「流れる」「流れない」は、単純そうでとても奥が深い世界です。
身近な金属やプラスチックの違いを理解することが、電気の基礎理解への第一歩です。





電気の通り道を意識すると、身の回りの“当たり前”がちょっと違って見えてくるね。





そうですね。次は第2章『電流の磁気作用』に進みますよ。
フレミングの法則は覚えていますか?





名前だけは、なんとなく憶えてるけど、、、ところで!Lesson3の後半に接地抵抗っての書いてあったような気がしたけど、今回、全然触れてないけど大丈夫?





📘 今回(Lesson3)内に出てくる「接地抵抗(せっちていこう)」の話題は、
わずかに「抵抗」という流れの中で軽く触れられているだけで、本格的な“接地抵抗の測定”や“接地工事”の内容ではありません。
🔍今回の「接地抵抗」の扱い
「導体・絶縁体」「抵抗率」「温度と抵抗」などの解説のあとに、
欄外や表中で「接地抵抗(大地の抵抗)」という言葉がチラッと出ていましたね。
ただしその部分はあくまで:
「大地にも抵抗があり、それを接地抵抗という」というレベルの用語紹介程度です。
つまり、Lesson3の本題は「電気を通す・通さない」の基本であって、
「接地抵抗の測定値や規定(Ωの基準値)」までは踏み込んでいません。
⚡第2種電気工事士試験との関係
ここがポイントです👇
| 分野 | 試験での扱い | 学び直しの優先度 |
|---|---|---|
| 導体・絶縁体・抵抗率 | 筆記で必須(基礎) | ★★★★★(最優先) |
| 接地抵抗の概念 | ほんの基礎知識(抵抗の一種として) | ★★☆☆☆ |
| 接地工事・接地抵抗の規定(D種・C種など) | 実務・法規の範囲(別単元) | ★★★★★(後半で必須) |
つまり、
- 今のLesson3段階では、まだ「触り」だけでOK。
- 本格的にやるのは、後半です。
🤖とはいえ、今のうちに“軽く”理解しておくと役立つ!
今の段階で押さえておくべきことは、この3点だけで十分です👇
- 接地(アース)とは、電気を安全に逃がすために大地とつなぐこと。
- 大地にも電気抵抗がある。それが接地抵抗。
- 抵抗が小さいほど、電気を逃がしやすく「安全」。
🧩 例:落雷や漏電が起きたとき、電気が建物にとどまらず地面に流れるようにするための仕組み。
🧭まとめ:今は基礎理解だけで十分!
| 項目 | 学び直し必要度 | コメント |
|---|---|---|
| 導体・絶縁体 | 必須 | 電気の通り道を理解する基本 |
| 抵抗・抵抗率 | 必須 | 工事士試験の計算問題で頻出 |
| 接地抵抗 | 今は軽くでOK | 後の「接地工事」で本格学習 |





じゃあ、接地抵抗は“抵抗の仲間”だけど、今は触りだけでいい感じ?





そう!“大地にも抵抗がある”ってイメージを持っておけば、次に進むときスムーズだよ。





わかった!じゃあ今は抵抗の基本をマスターする方に集中するね。
📒今回学んだこと
- 導体と絶縁体の違い
- 抵抗率の意味と計算式
- 電線の長さや太さが抵抗に与える影響
- 温度と抵抗の関係がイメージ
この記事へのご意見・ご指摘・ご感想をお願いします
記事の内容は入念にチェックしておりますが、万が一、誤った情報や古い情報、解釈の違いなどお気づきの点がございましたら、遠慮なくサイト一番下コメント欄でご指摘いただけますと幸いです。
また、「勉強になった!」「私もそう思います」といった記事のご感想も大歓迎です。
皆さまからのフィードバックが、サイトの質を高める力になります。ご協力よろしくお願いいたします!
詳細な免責事項や広告に関するポリシーについては、[免責事項ページへのリンク]をご確認ください。